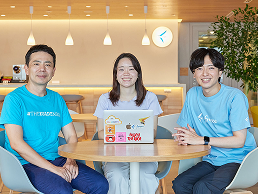ゼロからの挑戦を、家庭と両立しながら

個人向けマーケティング担当
磯貝美紀|2021年11月入社
『起業時代』統括編集長。前職でBtoB・BtoCマーケティング、プロダクト開発を担当。現在、『起業時代』アプリ・ブランド企画開発リーダー。双子男子高校生の母で「イキイキと働く大人があふれる社会を創りたい」がモットー。
転職の決め手となった”ミッションへの共感”
なぜfreeeへの転職を決めましたか?
ひとつは「スモールビジネスを変える」というミッションがいいなと思ったことが非常に大きいです。それまでは教育分野の会社で仕事をしていたのですが、自分の双子の子供たちが大きくなって「あと10年でもう社会に出るんだ」と思ったときに、「彼らの出ていく社会が、もうちょっといい社会だといいな」と思った。ちょうど自分の関心が移り変わってきた時期で、そのときに一発目に声をかけてくれたのがfreeeでした。
それからもう一つは「人」ですね。7人くらいの社員と面談する中で、とてもフラットな印象を感じました。前にいた会社が割とトラディショナルなタテ組織だったので、freeeの人はすごく自然体で、挑戦感や躍動感あり、みなさんすごい方ばかりなんだろうけど肩肘張らない感じで、面白そうだと感じたんです。
freeeで働いてみてどう感じていますか?
freeeに来てから、ずっと新しいことをやっている気がしてます。
アプリを作ったり、大学連携や地域連携をやってみたり。先日始めた「スモビのがっこう」という起業を学ぶオンラインの学びの場も、「そういうのあったら起業したい人たちが前に進みやすいよね」「じゃあやってみる?」という感じで始めました。色々新しいことを、次々にやってきています。起業界隈が変わっていく中で、既存の枠組みの中で「これがなきゃ」というよりはfreeeがやるべきことやミッションに対して良いと思えば「やってよし」という感じのところがあるので、好きに�挑戦させてもらっていて、同じことを繰り返してる感はないですね。
前職の経験はfreeeでどう生きていますか?
前職は教育関連の会社でマーケを軸足に、商品開発もやっていました。
例えばランドセルの開発をした時は、「世の中ではファッションランドセルが流行ってるから」ではなく、ランドセルって子供や親の思いから考えたらどういう存在なのだろうということを考えて、訴求やプロダクトに落としていくということをやっていました。ターゲットにあたる人にとって、その商品やサービスの「本質」は何か、どう伝えればそれが響くのか、をいつも考えていた気がします。
今の仕事では、アプリや雑誌を創ったり、学校に授業をしに行ったり、地域にアプローチしたりと、アウトプットはいろんな形をしていますが、真ん中で思ってることは前職時代と変わってないんです。例えば雑誌「起業時代」の編集も、これから起業したい方が何を思っていて、この雑誌がどうあれば彼らに響くのか、ということを常に考えています。freeeの対象は広いし、大人や学生がイキイキしている状態を作るために、起業という挑戦に置いて、私達がどうしたらサポートできるか。それを言葉やサービスに落としたらどうなるのか、まさにfreeeでいうところの「マジ価値」を、学生からシニアまでを対象に、方法を狭めずに考えています。
困難も感じたfreeeでのゼロからの挑戦

なぜ新しいことに挑戦できるんですか?
元々の性格は、比較的コンサバなんです(笑)新卒で入った会社はコンサバティブな通信会社ですが、3年目に新サービス開発のプロジェクトに抜擢してもらいました。そのサービスは当時においては革命的なサービスで。それに果敢に挑戦しながらめいいっぱい働く先輩たちの姿を近くで見ることができた。その時に、既存のあり方にとらわれず、挑戦することの面白さを教えてもらいました。当時はハードで、朝4時まで働いてタクシー帰りの時期もありましたが、ある意味、「大抵の仕事は大丈夫。なんとかなる。」と思える基礎が、20代の頃にできましたね。
そのあとに働いた教育関連の会社はDMを作って総括して、次の年またDMを送るという、リピートを丁寧にやる会社でした。私がいたのは新規事業の部署だったので、比較的新しいことをやる部署ではありましたが、根本にあるのは「リピートを大事にする」という思想。私自身は、同じことをやり続けるよりは「どんどん新しいことをやりたい、思考の枠組みを固くしたくない」という想いがだんだんはっきりしてきたんです。
転職してから壁やハードルはありましたか?
最初の会社で5年、前職で19年も働いていたので、ここまできてゼロクリアで私はやれるのか、正直葛藤やハードルを感じていました。入社してみたら周囲はみんな若いし、自由人の集まりといった感じで、堅めで細かく積み上げるタイプの人が多かった前職とは、環境も大きく異なっていました。11月に入社して最初の3ヶ月は家族も心配するくらいかなり落ち込んでいましたね。
夫は元々、私にコンサバな面もあることを知っていたから、「freeeみたいなIT企業に、やっぱり合わないのかな」って目で、たぶん見ていたと思います。一方で私が同じことの繰り返しを嫌がるのも分かっているので、様子見していたという感じですね。
その壁をどうして乗り越えられましたか?
当時、私は起業時代アプリの開発を担当していましたが、同じチームでやっていた雑誌に手つかずの在庫があることを知ったんです。それをどうするか、という話になった時、「『起業時代』は人の挑戦を応援する雑誌だから、自分用に買うだけじゃなく、応援したい誰かにプレゼントする、という発想があってもいいんじゃないか」と思った。そこで、大切な人に薔薇と本をプレゼントする、という「サン・ジョルディの日」というスペインの風習に載せて、雑誌をプレゼントするキャンペーンを提案してみました。すると、「やってみれば?」という感じでやらせてもらえて。
人の想いを大事にする、というこの企画は、私っぽくて自分でも納得してたし、やってみちゃえばいいよ!とやらせてもらえたおかげで、「この会社は目的さえ揃っていれば、自分で動いて自分で好きに挑戦していいんだ」と思えるようになりました。ターゲットとなる人、お客様は、この商品やサービスをどういった思いで手に取るのか。その奥底にある、本当の気持ちは何か。そこに響かせる、という、自分の培ってきたマーケ視点や、私自身の大事にしたいことが、この会社に来てから初め�て重ねられた企画でした。
freeeの中で成長できた経験はなんですか?
起業時代のアプリ開発から始まって、今は高校や大学で起業プログラムの授業もやらせてもらっています。起業手続きのノウハウの授業から、そのもっと手前のマインド醸成、つまりはアントレプレナーシップを育むようなプログラムまでやっています 。まさか自分が先生的な立ち位置に立つとは思ってもいなかったけど、学生たちの未来に向けて、直接メッセージを届けられるのは本当に貴重な経験だと思っています。彼らにどんな言葉を渡せば響くのか、伝わるのかを、一つひとつ考えています。
この子たちがいつか起業という市場を創ってくれるし、いつか一緒に働く相手になる。彼らにとって私の印象はfreeeの印象。自分の言葉や伝えることがfreeeが伝えたこととなって彼らに残る。大きな意味ではマーケティングであり、freeeのブランディング。そういうことも他社はやってない。マジ価値を大事にするfreeeだからこそ、チャンスを与えてもらえていると思っています。
家族とチャレンジの両立
今後チャレンジしてみたいことはなんですか?
どんなに大変でも、挑戦している人って、みんないい顔していますよね。
freeeの中の仕事で考えるなら、起業という挑戦をしている人を、この国にもっと増やしたい。
一方で挑戦することはやっぱりキツイし、時に折れそうになることも事実だと思うんです。だから、そういう時に寄り添える存在でありたいとも思っています。その�ために、個人的にキャリアコンサルタントの勉強も始めました。
ガンガン前に進むことができる時だけじゃなく、そうじゃない時も含めて、その人のキャリアや生き方に寄り添えるように。どういう状況においても、本当の意味で挑戦を応援する存在に、私自身も、freeeや起業時代も、なれたらいいな、と思っています。
この会社でも、そうじゃないところでも、自分がやれることはまだまだきっとあると思っています。
プライベートとの両立はできていますか?
平日は、朝10時くらいに出社して、20時頃に会社を出ますね。
高校生の子供二人も部活をしているので、ご飯を作って食べるのが22時になる時もあります。自分の帰りが遅くなる日は夕食を作ってから家を出ますし、出張の時は数日分、作り置きをしていきます。
仕事をしているのは家族の為でもあるけど、させてもらえているのは家族のおかげでもある。だから、「居られない時」は、家族が困らないよう、ある程度は(笑)、先に手を打っておくようにしています。
仕事と子育てを並行するようになって、そういう才能は伸びました!
日々、ドタバタだし、決して「満点の生活」ではないけれど、それでも何とかなる!そうやってるうちに、いつの間にやら子供達も高校生です。
今、高校向けに授業もしているので、子供を巻き込んで、ちょっと課題をやってみてもらったり、授業のコンテンツに意見をもらうこともあります。縁あって子供の高校に呼ばれて起業の話をしに行ったことも。子供たちも私が働く姿を見て、何かを感じ取ってくれていればいいなと思っています。